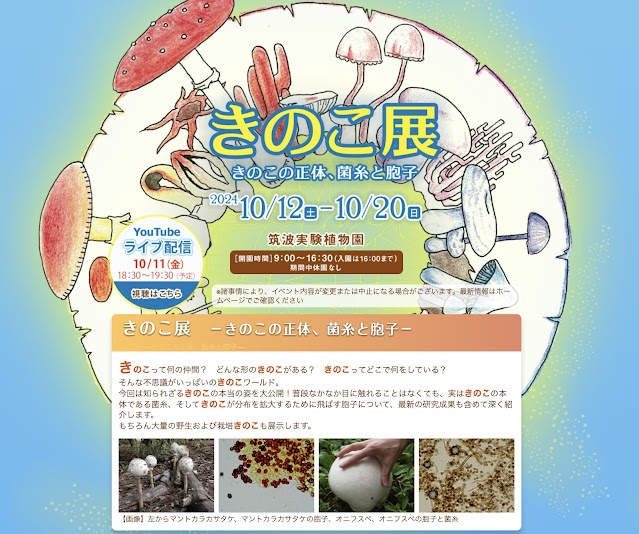昨年にコロナが5類に移行されてから初となる今年のゴールデンウィークでしたが、円安が祟り国内にとどまる人も多かったようです。
私の連休のほとんどは、ほぼほぼDIYパーゴラ作りで消化となりました。なにしろ晴れた日はのっぴきならない夏日となるので、日除けのためのパーゴラを作ってしまう必要があったのです。
やっつけパーゴラが完成したので、室内で冬越しさせていたビカクシダだのフペルジアだのエアプランツだのをやっと外に追い出すことができました。
シロアリ被害で腐ってしまったウッドデッキを撤去したあと、一番強く感じたことは「なぜもっと早く撤去しなかったのだろう・・・」でした。土はやっぱりいい! 昨今では土を嫌う人も多いのですが、土がもつ寛容性のおかげで生ごみは減らせるし、宿根草は植えっぱなしで花が咲きます。
鉢植えのバラは、水切れが一番の大敵ですが、土の上に直置きすると水分量が長く保たれて、水やりの回数も少なくなります。


緑肥を刈り取って土を覆ったりグランドカバー植物を生やしておくだけで、酷暑でも地温が30℃以下に保たれて野菜が夏バテせず収量が落ちなかったという農家さんも。庭に土があると、いいことづくめ!

パーゴラ作りで連休が消化されていく日々のなか、春の野原で展開するドラマチックな出来事の数々を経験しました。毎年シジュウカラが巣をかける巣箱が古くなったため、昨年の秋に新しい巣箱をセットしておき、この古い巣箱は低いフェンスにかけておきました。ところが4月になって親鶏がこの古い巣箱にエサを運びはじめたので、ひなが孵化したんだなと喜んでおりました。

ある日のこと、親鳥がけたたましい鳴き声をあげ警戒音を発していました。「もしや!」と思い、急いで外に出てみると・・・
3匹のアオダイショウが巣箱に侵入しようとしていたのです。慌てて巣箱を外し、ヘビの尻尾をつかんで引っ張り出そうとしましたが、ヘビは巣箱の中にスッポリ入ってしまい、ヒナは全て食べられてしまいました。
それにしても同時に3匹くるとは!

ヒナを救うことができず、非常に落ち込みましたが、ヘビだってそれはそれは可愛い存在です。巣箱の中からキラキラした目で恐々とコチラをのぞき、チョロチョロと舌を出して気配を伺っています。邪魔したことをよくよく謝ってから、離れた場所で観察していると巣箱からスルスルっと出て土留めの水抜きパイプに隠れてしまいました。

ところで、ウラの大きな木が伐採されると、庭全体に日がよく当たるようになりました。
バラの完全無農薬栽培をはじめて5年以上経ちますが「やっぱり無農薬栽培だと花つきを諦めないといけないのかな」と落ち込む年の方が多かったのです。
日当たりがよくなった今年、心の底から思い知りました。「バラは、耐病性だの品種だの手入れだのスキルだの、ではなく日当たりがよければ勝手にたくさん咲く!!! 」


15cm足らずの挿し木でスタートさせた3年目のグラハム・トーマス。半日陰の悪条件でもよく咲きます。大苗でGETした親株は、2年前に枯れ腐ったというのに。


イングリッシュ・ローズは高温多湿な日本の夏が苦手だとよく言われますが、この英国製のテラコッタ・ポットに植えたすべてのイングリッシュ・ローズが、つるバラにできるほど大きく大きく育ちました。

しかし、植物がよく育つ鉢ほど、よく乾く!
4月であっても夏日になると、たった1日で鉢が乾いて、バラが萎れてしまうことが何度かありました。ということで40cmほどの鉢皿をGETして水を溜めて底面給水にしました。酷暑が当たり前となってしまった昨今の夏は、問答無用で鉢皿に水を溜めるようにしたほうが正解だと思います。

ということで日当たりが良くなったおかげで我が家のバラどもは、どれも良く咲きました。めでたしめでたし。


緑肥として毎年種まきをしているクリムゾン・クローバーと宿根草のエキウム・ブルーベッターの青と赤のコントラストを見ていると、とても幸せな気分になります。

どんなにパラの葉っぱが虫に喰われてボロボロにされても無農薬栽培を続けていますが、人にも植物にも益虫である蜂やクモたちを見つけると、安易に農薬を撒き散らさずにいて良かったなと心から思います。




無農薬栽培の実践に大切なのは「無農薬で育てやすい植物や品種を選ぶこと」につきます。
桜や桃よりも梅! ミカンやオレンジよりもレモン!ですよね。


日本ミツバチを呼ぶと言われているキンリョウヘン。毎年咲くようになりました。それでも日本ミツバチの巣を見つけたことがないのは、5月に入って咲くので分蜂のピーク時期に間に合ってないようです。


連休中に訪れた城ヶ崎。海岸沿いのハイキングコースは大勢の観光客たちで大渋滞でした。しかも聞こえてくるのは、ほぼほぼ中国語!!

岸壁沿いの岩場に自然に芽生えた赤松たちは、まるで盆栽でした。
土がほとんどない岩場に生える松は、根っこから出す根酸で岩をじわじわと溶かしてミネラル養分を吸収して育つんだそうです。
ハイキングコースには、巨大なクワズイモが転がっていました。クワズイモといえば、人気もお値段も高い観葉植物です。
見上げれば巨大なクワズイモが斜面に生息しておりました。
「そういえば、横須賀の城ヶ崎公園にも巨大なクワズイモが自生していたよねぇ! 城ヶ崎?城ヶ島? 今歩いてるのはどっちだっけ?」