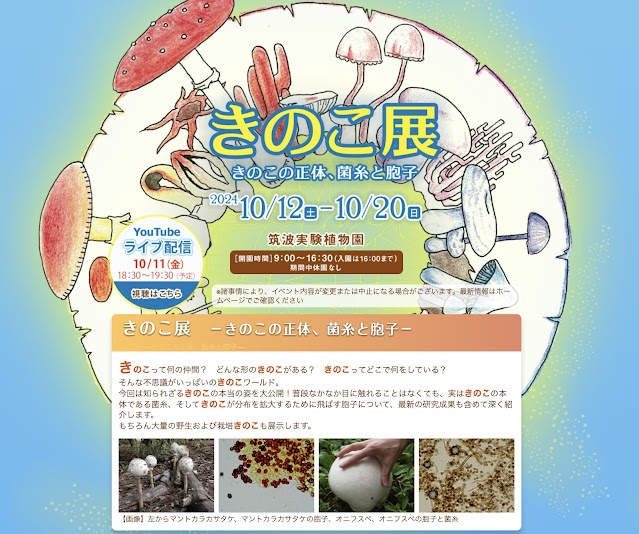COVIDのせいで、ここ数年行けていなかった筑波実験植物園のキノコ展に足を運びました。
(現在キノコ展は終了していますが、植物園には入場できます)
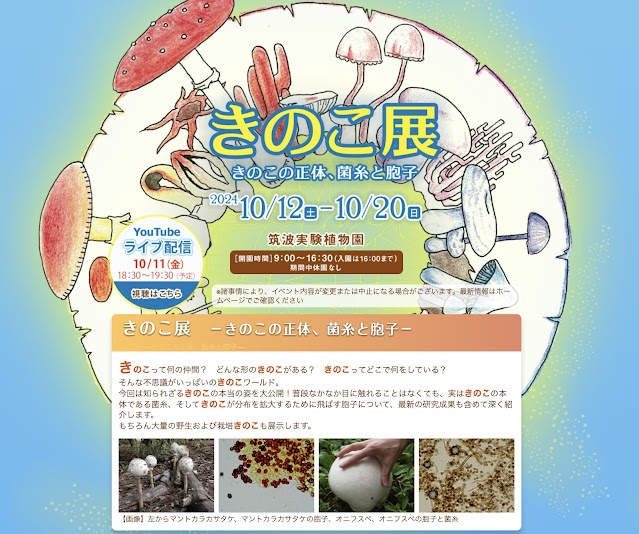
まずは園内敷地に自生していた巨大な「シロオニタケ」がお出迎えしてくれました。
この存在感は、なかなか出会えません。

栽培キノコの展示テントには、それはそれはウマそうな菌床栽培のキノコどもがずらり。圧巻でした。


ブナシメジの群れ。

ヒラタケシメジ・・・たしか、たぶん。

重厚感あふれるカーテンのようなエリンギ

モリモリとしたキノコたち。

「原木シイタケ」対「菌床シイタケ」の比較もできる。


栽培キノコ達を心ゆくまで愛でたので、園内をテクテク散策していると、なんと自生キクラゲに出会いました。室内で過保護に育てているとウンでもスンでも生えてこなかったキクラゲ菌床栽培キット。収穫をすっかりあきらめてカピカピに乾いた頃に、菌床ごと屋外追放して雨ざらしにしたらワサワサと生えてきた思い出があります。

天然のテラリウム。マイナスイオンを感じます。

浮世絵のようなカワラタケ。サルノコシカケ科のキノコ類は抗癌作用などが有名ですが、このエキスには植物の免疫力を高めるパワーも秘めています。このエキスには、真菌類が侵入してきたと誤解させる成分が含まれるからなんですねぇ。バラの免疫力も強化されるかテストしてみたいと思います。

キノコ展を堪能したので、温室に足を踏み入れてみました。
「おいおい、これはビカクシダかい?そうのなかい?」
と思わずつぶやいた巨大なビカクシダ。

ニポンジンは、ほんの数年でビカクシダ栽培をすっかり習得いたしましたね。
早く大きく育てるには、おもいのほか光が必要ですよね。おうちでビカクシダを確実に大きく美しく育てようとするならば、胞子をたくさん採取したいのならば、100W前後の栽培用LEDはマストアイテムですね。

「しゅみえん」にも出演なすったらしいビカクシダ。
「プラティケリウム・コロナリウム」

植物園でいま、本当によく目にするのがコイヤーマットを土留めとして活用している様子です。
巨大にそだつ植物は、大きくなればなるほど移植が大変になるし、頭でっかちに育つと根元がグラグラ不安定になり倒れやすくなってしまいます。さらに、鉢植えにしてしまうと、ゲリラ豪雨での流出や、植物自体が土を吸収してしまい、土がどんどん減るんですよねぇ。
このようにコイヤーマットを根のまわりにグルリと巻いけば、土を足して根元を安定させて倒伏を防いだり、根の保護もできるってわけです。
ユッカ、アガベ、オージープランツなどスタイリッシュな植栽やアジサイなどの花木類を鉢植えで育てている方も多いと思います。植えっぱなしの鉢植えは、土が減ってきたと感じたら、根元に土を足してあげると不定根が新たに伸びて安定するし、よいコンディションをずっとキープできるし、真夏でも土の乾きがゆるやかになり水やりに追われることも減るし、大きな鉢に植え増ししてあげなくてもよくなります。仕上げとして表土に市販のココチップをギッチギチにマルチングしてあげると保水効果がアップするだけでなく、見た目がリフレッシュできるのでおすすめです。無機用土の化粧砂よりも有機質のマルチング資材のほうがじっくりと土に還るので微生物層も豊かになって理想的だと感じています。
訪れるたびに新たな発見と感動がある筑波実験植物園。おすすめです。