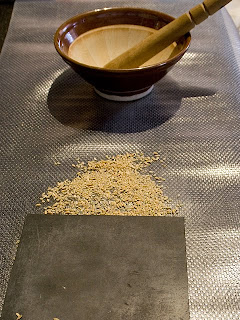もちろんその成果は、オランダが国をあげて農業対策とか設備の開発に力を注いできたおかげでもあったり、オランダの施設栽培のやりかたに適した品種の開発にチカラをいてれることも大きいそうです。
ところが、利益のうすい施設農家さんや小規模農家さんなどの廃業が毎年 0.5% ほどだそうです。手放された農地を、チカラのある農家さんたちがどんどん買い取り巨大化してる実情もあって、農家さん一件あたりの栽培面積は、年々拡大していく傾向にあるそうです。
そして以前のオランダでは、味や品質よりも「とにかく量だ! 量をとってガンガンもうけるぞ!!」だったらしく、おもに養液で育てられたオランダのトマトは、他国から「 味がみずっぽくて果肉がブヨブヨの水トマト 」なんて、ありがたくない評価だったそうです。( いろんな事情で半分ヤッカミもあったのかもしれませんが。 )
しかも昨今の「オーガニック最高! オーガニックじゃなきゃあ! 」の有機栽培ブームのアラシが吹き荒れたり、野菜があまってしまって価格が下がったりで「 高く売れる野菜をつくるぞ ! 」となったようで、だんだんと付加価値のたかい無農薬や減農薬栽培に方向転換してったそうです。
そのうえ、廃業した農地の買い占めて統合されたり、土地の安い新天地へ移動していったりで、農家さん一件当たりの栽培面積が年々だだっぴろなってくなか、ぜぇ〜んぶヒトの手や薬剤のチカラで最適に保つことはムリすぎるので、温度、湿度、風量、水やり、炭酸ガスの添加まで、すべてコンピューター制御で植物の生長から開花期への切りかえ、はたまた果実サイズと味までコントロールできちゃってるそうです。
ガラスハウスで働くヒトたち全員が端末を持って作業するので、管理するヒトがコンピュータの前に座れば数ヘクタールのグラスハウスの様子が、まるまる把握できるってぇいう徹底ぶりです。
なので、積算温度で熟すトマトなんかは「もちょっと、大きくしたいな」という時は室温を下げて登熟期間を長めにのばして実を大きくしたり、逆に室温を上げて収穫までの期間を早めて出荷スケジュールを調整したりと、自由自在っってカンジなんですねー。
ところで、何でビニールハウスじゃなくてガラスハウスなの? ってことなんですが、高緯度にあるオランダは日本に比べると冬のあいだ2時間も日が短いです。
それでも夏野菜のトマトが世界一輸出できてるのは、HPSランプなどグロウランプによる「 補光栽培 」がさかんなおかげもありますし、「 日光を最大限に利用して、とことん光合成量をふやす!! 」っていう技術が徹底してるからだそうです。なので、日光をよく通すガラスでグリーンハウスをつくったんですねー。ガラスハウスの屋根は定期的にキレイにお掃除して、光をよく通すように管理されてたり、葉っぱの数をコントロールして光合成量が最大になるよう葉面積を管理してるそうです。
あと施設栽培では、肥料としてのCO2/炭酸ガスを添加するシステムがとても充実してるそうで、日中は午前中を中心にず〜っと650ppmの濃度でCO2を添加しつづけてるそうです。
・・・ん〜なるほど。作物の生長を数値でコントロールしたり、あらかじめ儲からない施設投資はしなかったりと、ムダなコストを徹底的に省いてるんですね。学ぶところは、ホントにたくさんあります。ワタシとしては「基本知識」をちゃんと抑えたうえで、自分のやり方をつらぬいて奇跡をおこしちゃった「木村さん」のように、常識にとらわれない自由な発想で育ててみるやり方にも大きな魅力を感じます。